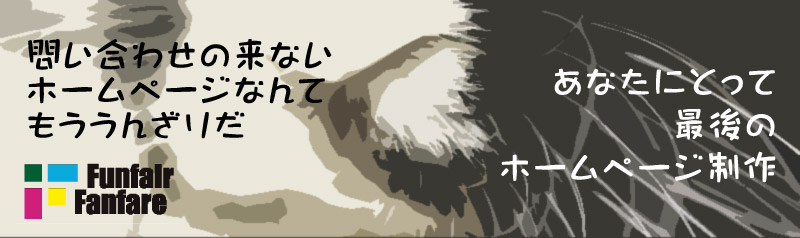弦高
「弦高」について、用語の意味などを解説

弦高とは、弦楽器における弦とフィンガーボードとの距離の事。演奏性や音質を大きく左右する要素である。ギター、ベース、バイオリン、チェロなど、あらゆる弦楽器に共通して用いられる基本的な用語である。
弦高が高い場合、弦を押さえる際に強い力が必要となるため、演奏の難易度は上がるが、その分、弦の振動が大きくなり、音量やサステイン(音の伸び)が豊かになる傾向がある。一方で弦高が低いと、軽いタッチで演奏しやすくなる反面、弦がフレットや指板に触れて「ビビり(雑音)」が発生しやすくなる。したがって、弦高の調整は演奏スタイルやジャンル、奏者の好みによって最適値が異なる。
クラシックギターでは、音の深みと安定性を重視してやや高めの弦高が選ばれることが多いが、エレキギターやベースでは速いパッセージを弾きやすくするために低めの設定が好まれる。バイオリンやチェロのような擦弦楽器では、弓の圧力とのバランスを考慮して弦高が微調整され、音の立ち上がりや音色のコントロールに影響を与える。
「弦高とは」音楽用語としての「弦高」の意味などを解説
Published:2024/04/19 updated: