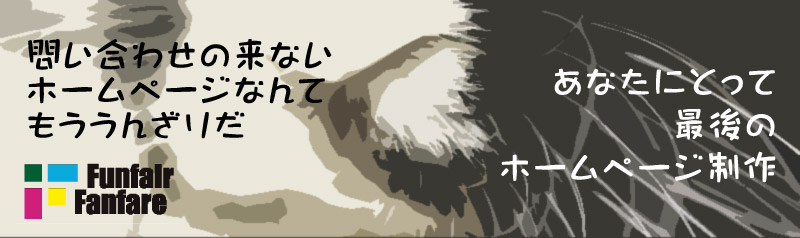ネウマ
Posted by Arsène
「ネウマ」について、用語の意味などを解説

neuma(ラ)
ネウマとは、中世の単旋律歌曲の記譜で使われた記号。旋律の動きや演奏上のニュアンスを視覚的に示そうとしたもの。
音楽用語 Related
- ア・カペラ a capella(ラ) ア・カペラは、楽器伴奏のない合唱曲。アカペラと表記されることもある。元は、簡素化された教会音楽の様式や楽曲を指し、「礼拝堂風(聖堂風に)」という意味を持つ。...
- 嬰記号 sharp(英) 嬰記号とは、音の高さを半音上げる変化記号。記号は♯(シャープ)を使用。...
- オーパス opus(ラ・英) オーパス=「作品」の意。省略形の「op.」の後に番号を付け、作品番号を示す。オプス。 「Op.」と表記されることがあるが、元々ラテン語のため、本来は小文字で表記する方が正しい。17から18世紀において…...
- ビス bis(ラテン) ビスとは、短い小節の反復に用いられる記号。...
- フォルテ forte(伊) フォルテ=強く。fと略記。強弱記号のひとつ。力強い。音量を大きく、強く。丈夫な。激しい。 メゾ・フォルテ フォルティッシモ フォルティッシッシモ(フォルテフォルティッシモ) フォルテピアノ ピアノフォル…...
- フォルティッシッシモ fortississimo(伊) フォルティッシッシモ=フォルティッシモよりさらに強く。fffと略記。フォルテフォルティッシモ。 メゾ・フォルテ フォルテ フォルティッシモ...
- フォルテピアノ foltepiano(伊) フォルテピアノとは次のような意味を持つ。 (1)強く、直ちに弱く。フォルテ(f)で演奏した直後にピアノ(p)。fpと略記。 (2)楽器の名称。特に18-19世紀にかけて存在した初期のピアノを指…...
- フーガ fuga(ラ・伊) フーガとは、冒頭に提示された主題が、複数の声部間で対位法に、次々と規則性をもって模倣反復される楽曲。全体は、主題とその応答からなる提示部と、エピソードとの交替で構成される。語源としてはラテン語の「fu…...
- 付点音符 dotted note(英) 付点音符とは、音符の右側に点のついた音符。付点音符は、元の音符の音価の1/2の長さが加えられる。...
- フラット flat(英) フラットとは、音の高さを半音下げる事。あるいは音の高さが半音下がっている事。変記号(♭)。...
- 変記号 flat(英) 変記号とは、音の高さ半音下げる変化記号。記号は♭を使用。フラット。...
- ミサ曲 missa(ラ) ミサ曲は、ミサで歌われる音楽、特に通常式文の「キリエ」「グロリア」「クレド」「サンクトゥス」「アニュス・デイ」の5章をまとめて、合唱組曲の様に作曲したもの。...
- メゾ・ピアノ mezzo piano(伊) メゾ・ピアノ=少し弱く。mpと略記。 強弱記号の一つ「ピアノ=弱く。静かに」の頭に「メゾ=半分くらい」を付け、「メゾ・ピアノ=少し弱く」という意味となる。強弱としてはピアノよりやや強い。 メ…...
- メゾ・フォルテ mezzo forte(伊) メゾ・フォルテ=少し強く。mfと略記。 強弱記号の一つ「フォルテ=強く」の頭に「メゾ=半分くらい」を付け、「メゾ・フォルテ=少し強く」という意味となる。強弱としてはフォルテよりやや弱い。 フ…...
- 臨時記号 accidental mark(英) 臨時記号(りんじきごう)は、曲の途中において、音高を一時的に変える記号。 実際には変化記号(シャープ、フラット)や本位記号(ナチュラル)が用いられ、音符の左側に記される。 また注意点…...
- レガート legato(伊) レガートとは、音をつなげて、音の間を切れ目なく演奏する事。結ばれた、繋がれた、結ぶ、結びつけるという意味がある。なめらかに。「スタッカート」の対語。 ノンレガート 「点」を「線」に変える錯覚の美学 レ…...
- オプス opus(ラ・英) オプス → オーパス。作品番号。...
- ブレヴィス brevis(ラ) ブレヴィス=現代の二全音符(倍音符)。中世ルネサンス時代の全音符。 セミブレヴィス ブレーヴェ...
- セミブレヴィス semibrevis(ラ) セミブレヴィス=現代の全音符。中世ルネサンス時代の二分音符。 ブレヴィス...
- ミニマ minima(ラ) ミニマ=現代の二分音符。中世の四分音符であり、「最小」を意味する。...
「ネウマとは」音楽用語としての「ネウマ」の意味などを解説
Published:2024/04/25 updated: