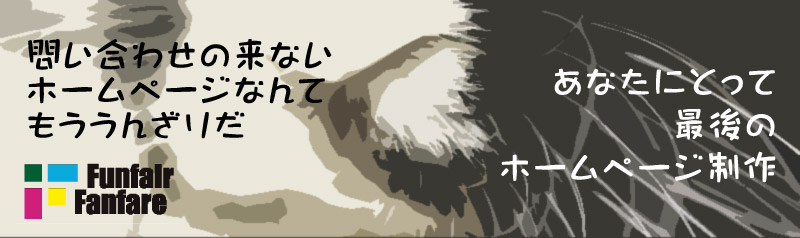音名
「音名」について、用語の意味などを解説

pitch name(英)
音名とは、音楽に関わる各音の高さに対して付けられる固有名。日本語ではハ-ニ-ホ-ヘ-ト-イ-ロ、ドイツ語ではC-D-E-F-G-A-H。ピッチネーム。
階名が相対的な音の高さであるのに対して、音名は絶対的な音の高さとなる。
音名とは、音楽理論において各音の高さを区別するために付けられた固有の名称であり、世界中の音楽教育や楽譜記譜法の基礎を成す重要な概念である。音名は音の絶対的な高さを示すもので、たとえばピアノの「ド(C)」はどの曲でも常に同じ高さを指し示す。一方、階名(ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ)は相対的な高さを表すもので、調性(キー)が変われば同じ「ド」であっても実際の音高は異なる。このため音名は、音楽理論や調律、楽器製作、録音・編集などの分野で「基準」として扱われることが多い。
日本語では「ハ・ニ・ホ・ヘ・ト・イ・ロ」と呼ばれる伝統的な音名があり、これは西洋のC・D・E・F・G・A・B(またはH)に対応する。たとえば、「ハ長調」はCメジャー、「ト短調」はGマイナーを意味する。このような日本語音名は、明治期に西洋音楽理論が導入された際に体系化されたものであり、古典的な和声理論や教育現場で今も広く使用されている。
ドイツ語圏では、BとHを区別する独自の表記体系が用いられる。具体的には、英語での「B♭」がドイツ語では「B」、「B(ナチュラル)」が「H」とされる。この違いはバッハの時代から存在し、彼の名前をモチーフにした「B-A-C-H(シ♭・ラ・ド・シ)」の音型など、作曲技法の中にも取り入れられている。英語圏ではC–D–E–F–G–A–Bの表記が主流であり、国や教育体系によって若干の違いが見られる。
また、音名には「絶対音高」としての側面もあり、国際的にはA4(中央のラ)を440Hzと定める「国際標準ピッチ(A=440Hz)」が用いられている。オーケストラのチューニングや録音の基準もこれに基づいて行われることが多い。ただし、古楽器演奏や時代様式の研究においては、A=415HzやA=430Hzなど、当時の音律や地域差に合わせたピッチが採用される場合もある。
音名は音楽理論と実践を結びつける言語的・物理的な基準として機能している。演奏家にとっては音程の理解、作曲家にとっては調性構造の把握、そして録音エンジニアにとっては周波数の認識に直結する概念であり、音楽という普遍的な言語を共有するための共通土台となっている。
「音名とは」音楽用語としての「音名」の意味などを解説
Published:2024/04/18 updated: